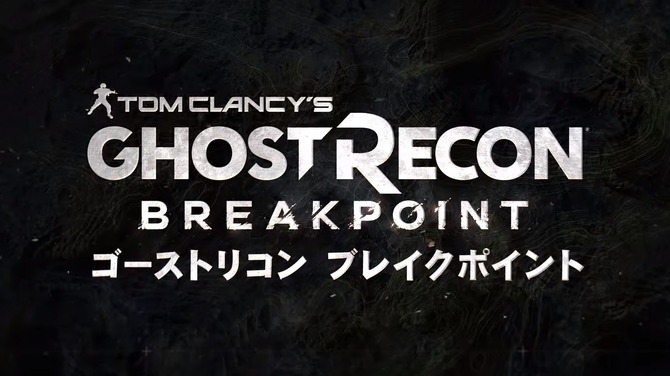 特殊部隊……聞くだけでときめいてしまう言葉ですよね。ときめきませんか?ならばもう一度、できれば音読してみてください。特殊部隊。ほら!!特殊部隊……ワクワクした?そうですよね、仕方ないと思います。男の子ってこういうのが好きですもんね。
特殊部隊……聞くだけでときめいてしまう言葉ですよね。ときめきませんか?ならばもう一度、できれば音読してみてください。特殊部隊。ほら!!特殊部隊……ワクワクした?そうですよね、仕方ないと思います。男の子ってこういうのが好きですもんね。これまで数多のミリタリーシューターがリリースされてきました。最近ではサバイバル系ゲームのように、必ずしも強いキャラクターを操作するとは限らない場合も増えてきましたが、せっかくゲームとして特殊な体験をするのであれば、特殊な訓練を受けた屈強な戦士として敵をバッタバッタとなぎ倒し、やっぱり自分は特殊なんだと感じたいですよね。
 まもなく発売される『ゴーストリコン ブレイクポイント』は、そんな特殊部隊を題材としたシリーズ最新作です。最新鋭のドローン技術を研究する天才科学者が、自然豊かな「アウロア島」を拠点にして、人類のテクノロジーを進展させようとしている近未来が舞台。しかし、特殊な悪いヤツがドローン技術を奪ってしまうという事件が起こり、有望であった研究は一転して危険な軍事力となってしまったのです。
まもなく発売される『ゴーストリコン ブレイクポイント』は、そんな特殊部隊を題材としたシリーズ最新作です。最新鋭のドローン技術を研究する天才科学者が、自然豊かな「アウロア島」を拠点にして、人類のテクノロジーを進展させようとしている近未来が舞台。しかし、特殊な悪いヤツがドローン技術を奪ってしまうという事件が起こり、有望であった研究は一転して危険な軍事力となってしまったのです。特殊部隊である「ゴースト」は、事態の解決という特殊任務を受けてアウロア島へ向かいます。しかしながら部隊は次々と撃破されてしまい、一気にピンチを迎えることに。なんと、敵のボスこそ「元ゴースト」隊員という特殊な敵だったのだ!!というストーリー。
メッチャときめいてきました。特殊部隊しかいません。全員が特殊である場合は、それを特殊と呼ぶべきではないのでは?否、呼ぶべきです。彼らは特殊な訓練を積んできているからこそ特殊足りえるからです。
特殊訓練を受けに「田村装備開発」さんへ
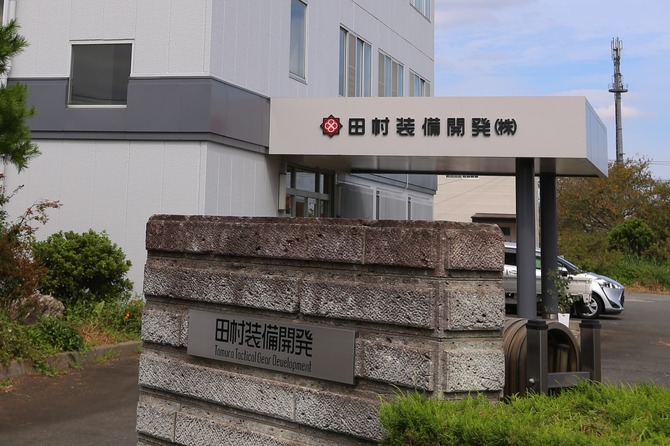
筆者を含めて、多くのゲーマーはいくつもの「特殊部隊」を体験してきました。しかしながら、それはあくまでも画面の中の演出です。彼らがどんな訓練を積み重ねてきたのかを実際に知ることは少なかったのではないでしょうか。
サバゲーを経験された方ならば、マガジンのリロードひとつとってみても「敵を目の前にして、あんなにスムーズな交換は出来ない」と実感されたことがあるかもしれません。マウスさえ動かせば正確に射撃できるその腕前や、作戦地域へ颯爽とヘリからロープで降り立つ姿などは、ゲームの中だからこそ当たり前のように体験できるものです。
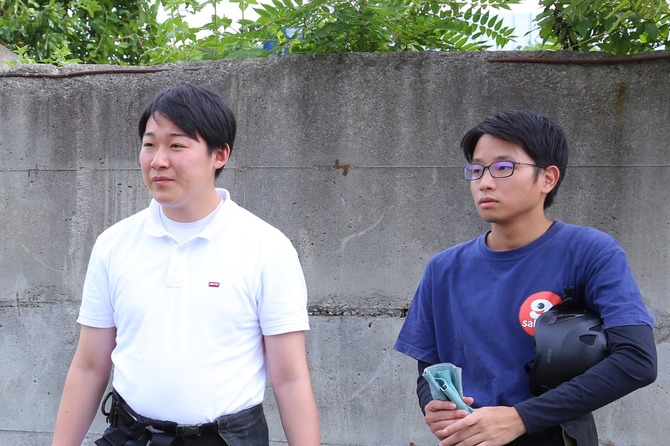
操作するキャラクターは特殊部隊としての訓練を受けているからこそ、そのような動きを可能としているはず……ならば、それらを少しでも理解できれば、プレイヤーとしてよりゲームを楽しめるようになるのではないか。
そのように考えた編集部は実際に特殊訓練を受けてみることにしました。お願いしたのは「田村装備開発」さんです。埼玉県東松山市を拠点とし、各種トレーニングを開講したり、様々な装備品の開発・販売を行っています。
トレーニング以外の技術指導の例として、アニメ作品「劇場版 PSYCHO-PASS:Sinners of the System Case.3」の劇中に登場する銃撃戦を監修し、リアルな作画に貢献するといったお仕事もされていたそうです。

この日、訓練を実施して下さったのは統括部長の長田賢治さん。
長田さんは、陸上自衛隊十数万人の隊員の中でも8%程度しか保有していないといわれる「レンジャー」隊員であり、その資格を修得する過酷な訓練では首席で卒業されました。
その後、防衛庁長官直轄部隊「特殊作戦群」(当時)に在籍されていたという驚くべき経歴もお持ちです。
ちなみに特殊作戦群の選抜は過酷な訓練を乗り越えたレンジャー隊員でさえ乗り越えるのは至難の業とのことです。
――この度はお忙しい中ありがとうございます。『ゴーストリコン』シリーズは特殊部隊の行動を体験するゲームなのですが、実際の特殊部隊ではどんなことをしているのでしょうか。
長田さん私はFPS系のゲームはあまりやらないのでなんとも言えませんが、特殊部隊の活動は皆さんがイメージするような、例えば映画などとは少し違うと思います。
詳しくはお話しできませんが、特殊部隊の行動を一言で言うなら「常に国益を考えた行動」です。そのことを規範とし、彼ら(特殊部隊員)は遠い未来を見越して活動しており、それはとても地味な業務ばかりです。
それらの業務は、なにかゴールが決まっていて、それを達成して終わりというものではないような気がします。なので、ひたすら訓練・検証を行い、あるかもしれない事象に対し、いつでも対応できる体勢を取りつつも、未来を想像して次なる訓練を企画していく、とても地道なものです。

──ゲームばかり見ていると、戦闘技術に特化した人達なのだと思い込んでしまいますね。
長田さんもちろんそうした技術も必要ですが、特殊な作戦というのは、様々な状況に即座に対応しなくてはなりませんので、一見、戦闘に必要でない知識や技術さえもとても重要になります。簡単に言えば引き出しが多ければ多いほど(様々な知識・技術を持ち合わせれば持ち合わせるほど)いいということです。
逆に戦闘だけに特化していると、その他の対処に遅れが生じたり、ダメージを負ったりしてしまい、結果的に任務遂行が困難になる可能性が高まります。
戦闘のことばかり注目してしまえば、そのほかの想定外が生まれてしまいます。限られた状況や方向性だけを想定するのではありません。身につけた様々な知識・技術を、見たまま、聞いたまま、感じたまま、目的に応じて活用し、邁進して達成する者こそが優秀な特殊部隊員といえます。
専門的な技術を見れば様々あるのですが、中心にある大事なものはそれほど複雑ではありません。私たちが実施している訓練の中で、「合理的行動」「ラペリング」「護身術」は大切な基本として繰り返し実施しています。何年も通われている受講生は、そのことをよく理解くださっております。
──本日は「護身術」と「ラぺリング」を実施して頂けるとのことですね。
長田さんはい。午前中は道場で護身術を学びます。午後は「田村トレーニングセンター」に移動して、15メートルのタワーからロープで降りていく訓練です。あ、はじめに言っておきますが「護身術」のバロメーターは「痛み」です!
道場でその技の本質を体感せよ!護身術入門

訓練日程は予め決められている為、一般の受講生の中に混ざって参加させて頂くこととなりました。長田さんの指導を聞き、実際に受講生同士で技を掛けあう形で訓練が続きます。
そのすべてをここでは紹介できませんが、人間の体の構造を理解・活用した格闘術のようなものでした。何となく合気道の紹介を見ているようでもあります。しかしながら、体の構造を利用して相手を動けなくするということは、当然そこに無理を生じさせることになります。つまり、「痛い」のです。


技を掛ける側はほとんど力を必要とせず、こんなことで成人男性が簡単に倒れてしまうのかと驚きっぱなしの編集部。練習の合間、一般の先輩受講生からも指導を受けつつ上達に励みます。
一緒に参加しているとはいえ、一般の方の邪魔をしてしまっては……と考えていると、長田さんは「指導するのも訓練になります」とひとこと。よく見てみれば、参加者のレベルにはかなりの差があり、長田さんは自身での指導とは別に、誰が誰を指導するのかを細かくチェックしながら、楽しくなるように声掛けを続けていました。
 「田村装備開発」で行われる訓練は、その日の参加者で内容が変わることもあるそうです。この日のように、全くの初心者から何年も通っているベテランまでもが、同じ場所で、かつそれぞれの目標を明確にしながら取り組めるのは、非常に高度なことだと感じます。
「田村装備開発」で行われる訓練は、その日の参加者で内容が変わることもあるそうです。この日のように、全くの初心者から何年も通っているベテランまでもが、同じ場所で、かつそれぞれの目標を明確にしながら取り組めるのは、非常に高度なことだと感じます。先鋭的な技術を磨く場合にはそうもいかないとは思いますが、あくまでもこれらの訓練は「いつまでも求め続ける本質的なもの」なのかもしれません。

時折挟まれる講義の中で長田さんは、どれだけ訓練を積んだとしてもリアルな現場で相対した人間には、こんなにキレイに決まるものではないと念を押し、また、護身術の最大の肝は「逃げること」だとも言います。
しかしながら、時において逃げる訳にはいかない状況があります。そんな時にどう考えるかが重要なのだそうです。いくら技術があっても、本質的なところで間違えてしまっては意味がありません。
そこで紹介されたのは、剣道にある「四戒」という考え方でした。「驚(おどろき)」「懼(おそれ)」「疑(うたがい)」「惑(まどい)」の念が生まれた時に、人間の隙ができるというものです。痛みなどで瞬間的に驚くと、人間の体は硬直してしまい、倒すのがとても簡単になるのだそうです。
その為、学んだ護身術で与えた痛みは「瞬間で最大に」「継続して与える」ことが肝心だという結論に至ります。ゆっくり痛みを大きくしても、途中でやめてしまっても、相手の心を折れずに、反撃を許してしまうという訳です。

ひとたび逃げずに立ち向かうと思ったのなら、「一気に相手へ近づく事」が安全を確保する可能性を高めるのだと言います。訓練されていない人は、恐ろしい状況が現れた時に、最も危なくなる選択をしてしまうのだそうです。
恐ろしさのあまり、その場で後ろ向きにしゃがんでも、ただ相手にやられてしまうだけ。中途半端に距離を取っても、最大の攻撃を繰り出す余裕を相手に与えるだけ。結局は、一見危ないように見えますが、相手の最も弱いところ(背面など)に素早く入り込むことが、可能性の高い選択に繋がっていく……ということになるんですね。

「命綱=左手」ラペリング訓練に挑む

ミリタリーシューターっぽさといえばラぺリングですよね。ロープ一本で様々な場所から急速に降下していくシーンは、必ずと言っていい程に登場します。
とはいえ、よほどミリタリー知識に興味がなければ、正確なラぺリングの構造まで知ることはほとんどないでしょう。始める前に「ラペリングは左手だけで制御できる」と聞かされましたが、しばらくはイメージできませんでした。
 金具にひっかける形でロープを通し、抵抗を発生させます。ロープの先を左手で握って、その強弱(または角度を付けること)で降下速度を制御します。慣れていけば、ほとんど握力を使わなくとも停止できるそうです。
金具にひっかける形でロープを通し、抵抗を発生させます。ロープの先を左手で握って、その強弱(または角度を付けること)で降下速度を制御します。慣れていけば、ほとんど握力を使わなくとも停止できるそうです。染谷いわゆる「命綱」的なのは……
長田さん無いですね。絶っ対に左手を離さないでください!
 とは言え、はじめのうちは長田さんによる命綱(白いロープ)を付けての体験となります。受講生はもちろん、長田さん、カメラマンもしっかりと命綱のフックを掛け、訓練を実施する度に指差呼称を行います。安全管理は絶対に欠かしません。黒いロープがラぺリングに必要な本来のロープです。実際にはこれ一本で実施することになります。
とは言え、はじめのうちは長田さんによる命綱(白いロープ)を付けての体験となります。受講生はもちろん、長田さん、カメラマンもしっかりと命綱のフックを掛け、訓練を実施する度に指差呼称を行います。安全管理は絶対に欠かしません。黒いロープがラぺリングに必要な本来のロープです。実際にはこれ一本で実施することになります。
降下開始地点にはつま先で立ち、ロープのテンションを確認します。支点から体に伸びるロープがしっかりと張っていれば、体重を後ろに掛けることができます(もちろん、左手はしっかり握った上で)。
そのまま脚をまっすぐ伸ばし、お辞儀をするように腰を折っていくと、ゲームでよく見かける「壁を蹴りながら降りるアレ」の姿になります。

開口部から降下地点までは15メートルという高さを誇るラぺリングタワー。上から見下ろした時の高さの感覚は想像以上でした。ロープが張っている感触があるからこそ、ゆっくりと降りていけるものの、ひとたび間違えれば単なるケガでは済まされません。
 すると、ひとりの受講生がロープのテンションもなしにスタンバイしはじめました。どうみてもロープがたるんでいます。右手もモデルガンを持って塞がっています。いやいや、まさか……
すると、ひとりの受講生がロープのテンションもなしにスタンバイしはじめました。どうみてもロープがたるんでいます。右手もモデルガンを持って塞がっています。いやいや、まさか……

15メートルの高さから重力加速度に従ってモノが落ちるのを見ることはそんなにありませんが、まさか人間で見ることになるとは思いませんでした。左手の制御が上手なおかげで、当たり判定がバグって表示がおかしくなったキャラのようになっていますが、どっちが地面だか分かりませんね。
※上記の降下訓練は「ラペリング特級」を取得している方が行うものです。

ラぺリングは様々な降り方があり、目的に応じて使い分けがなされます。ブランコのようにして窓を蹴破って突入するシーンは映画でも見かけますよね。この日は実際に、ラぺリングタワーの最上部(20メートル)から、ひと蹴りで開口部に飛び込むという訓練をしている受講生もいました。


限られた練習の合間にも関わらず、一般の受講生の方々が色んな降り方を実践して下さり、何度もアドバイスを頂いたりしながら、段々と上達していく土田と染谷。最後の方は左手の握力も尽きてしまい、ズルズルと落ちていくだけになってしまったものの、降りるだけならもうビビらないといった様子です。

長田さん「恐怖」は必要です。恐怖があるから強くなるとも言えると思います。恐怖なんか無いという人がいるなら、むしろ危険ではないでしょうか。毎日の訓練の中で、ロープを準備した後の「一本目の降下」は今でも怖いですよ。何度も点検・確認します。そういうものです。
 訓練を通して、受講生と長田さんの間には堅苦しい上下関係のようなものは感じられませんでした。楽しさと真剣さがうまく融合しているような、そんな師弟関係の存在する空間は、長田さんの正直さ、見栄の無さが創り出しているのかもしれません。
訓練を通して、受講生と長田さんの間には堅苦しい上下関係のようなものは感じられませんでした。楽しさと真剣さがうまく融合しているような、そんな師弟関係の存在する空間は、長田さんの正直さ、見栄の無さが創り出しているのかもしれません。「田村装備開発」では各種訓練へ実際に参加できます。午前・午後に分かれた訓練、または一日を使った特別訓練といった日程が組まれています。最近では、サバゲーでもっとカッコいい動きをしたい!という理由で参加される方も増えているようです。
訓練の無い日はサバゲーフィールドとしても定例会や貸出を行っており、幅広いレベルに合わせたサービスを柔軟に用意されているという印象を受けます。ひとつひとつの動きにきちんとした理由があり、それを深いレベルで活用できるなら、サバゲーが更に楽しくなりそうですね。
特殊訓練修了!『ブレイクポイント』へ備えよ!
 2019年10月4日から作戦開始!『ゴーストリコン ブレイクポイント』はPS4/Xbox One/PCで発売が予定されています。特殊部隊となって、元特殊部隊を相手に戦う本作は、様々な訓練を積んだキャラクターを操ることになります。長田さんの下で訓練を受けた我々なら、彼らの積み上げたものが分かるはず。ゲーマーとして、より力の入った遊び方ができるでしょう!!
2019年10月4日から作戦開始!『ゴーストリコン ブレイクポイント』はPS4/Xbox One/PCで発売が予定されています。特殊部隊となって、元特殊部隊を相手に戦う本作は、様々な訓練を積んだキャラクターを操ることになります。長田さんの下で訓練を受けた我々なら、彼らの積み上げたものが分かるはず。ゲーマーとして、より力の入った遊び方ができるでしょう!!同じ目標に向かって共に苦しい訓練を受けた仲間は、今でも忘れられない人達だと、長田さんは語ってくれました。Co-opシステムにより、4人までシームレスに入退場できる遊びやすさと、ソロプレイでも楽しめる「成長共有システム(PvE、PvPでキャラクター育成を共有)」で、高い自由度を実現した本作なら、そんな戦友も見つけられるかもしれません。

日々の業務と訓練でお忙しい中、丸一日みっちりと取材にご協力頂いた「田村装備開発」の皆様、ありがとうございました。また、同日に参加されていた受講生の皆様も、取材陣へ貴重なお時間を割いて指導にまで当たって頂きました。改めて感謝申し上げます。
『ゴーストリコン ブレイクポイント』は2019年10月4日、PS4/Xbox One/PC(Uplay、Epic Games Store)にて発売予定です。
詳しくは『ゴーストリコン ブレイクポイント』公式サイトをご覧ください。
※取材協力:田村装備開発 様
装備品や戦術戦技の研究・開発・販売、タクティカルトレーニング開講、アニメ・ゲーム等での技術指導、学校・企業等への出張指導、サバイバルゲームフィールド運営など、多岐にわたる事業を展開されています。詳しくは公式サイトをご覧ください。


































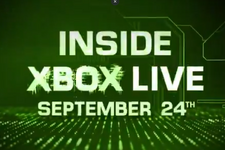














※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください