2021年8月24日から26日にかけて、国内最大のゲームカンファレンス「CEDEC2021」がオンラインで開催されました。本稿では、開発だけで手いっぱいになってしまいがちなインディーゲームデベロッパーを対象にしたセッション「はじめて書く!自分で書く!自社ゲームタイトルのプレスリリース」のレポートをお届けします。
登壇したのは、複数のゲームメディアでニュース執筆やインタビュー記事などの執筆を行うかたわら、中小個人のインディーゲームメーカーの広報支援を行っている一筆社の秦亮彦氏です。秦氏は、インディーゲーム、同人・学生サークルなどの小規模開発が盛んになっている今日、自らの手によるクリエイティブをリリースする喜びを享受する一方で「作ったのはいいけれど、このゲームをどうやって広めたらいいのだろう」と途方に暮れてしまう事例もよく発生していると語ります。
中規模・大規模の開発であればプレスリリースを発信するのは普通のことですが、小規模な現場では社内やチーム内にプレスリリースに関するノウハウがある人が1人もいない…というケースもめずらしくはありません。秦氏はそうした環境にある人たちに向け「プレスリリースを絶対に打つ必要はありませんが、やれば反響を得やすい。外注せずとも自分たちで作れるものですので、これも開発の一環ととらえてもいいと思う」と続けます。
かつて、Steamでおもしろいゲームを見つけてメディアで記事として紹介したところ、読者から確かな反響を得られたという秦氏。国内にあるデベロッパーがプレスリリースもSNSでの広報展開もしていなかったので取材を申し入れてみると、秦氏がメディアで取り上げたて販売数が増加したことに驚きと喜びをもって「よくぞこのゲームを見つけてくれました」と歓迎されたといいます。秦氏はそのとき「そうではないんです、あなたがたも折角のおもしろいゲームを見つけてもらえるよう努力すべきなんです」と返したとのことで、そのときの思いが今回の講演に繋がったと語りました。

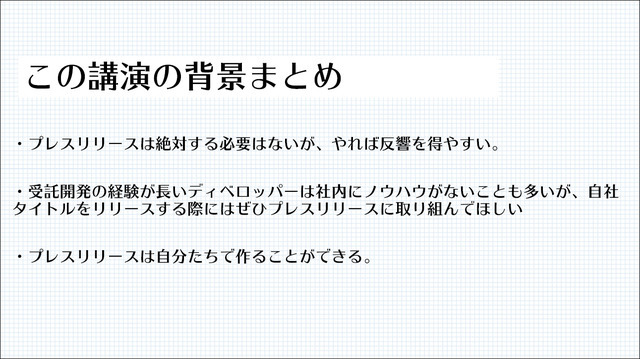
プレスリリースをなぜ打つのか
プレスリリースは、ユーザーに何らかのアクションを起こしてほしいときに打ちます。たとえば、公式サイトに来てほしい、ムービーやPVを見てほしい、体験版を遊んでみてほしい、予約してほしい……などがこれに当たります。


そうした目的が定まれば、公式サイト、SNSアカウント、プレイ動画、体験版など、あらかじめ用意しておくべきものも明確になりますし、リリース内にもそれらへのアクセス手段(公式サイトのURLや公式SNSのアカウント名など)を入れる必要があると自覚できます。

そして、1回のプレスリリースでいくつものアクションを要求するのは適切ではなく、目的に応じて複数回発信するのが大切です。秦氏はリリースを打つべきタイミングの一例として以下のようなものを挙げました。
タイトルの初発表
発売日の告知
プラットフォームページや公式サイトの公開
体験版の配信開始/告知
発売日当日
その他の情報

反対に、メディアに取り上げづらくなる要素、体裁としては
軽微なサイト更新情報
全体的に内容を盛り込みすぎのリリース
ゲームのスクリーンショットやキャラクターの画像など、絵素材がない
担当者の連絡先が書かれていない
などが挙げられました。また、Web媒体ではなく雑誌などの紙媒体への掲載を希望する場合は、絵素材の解像度にも考慮する必要があります。


プレスリリースの具体的な書き方
次に、プレスリリースの具体的な書き方が紹介されました。秦氏は「新聞の書き方に沿えばよく、特別な知識が必要とされるわけではありません」と語ります。具体的には
概要
ゲームの簡潔な紹介
ゲーム内容の詳細や開発の経緯
製品情報
自社情報
プレスキットの詳細、アクセス手段
で構成されるのが望ましいとしました。各項目について、具体的に紹介していきしょう。
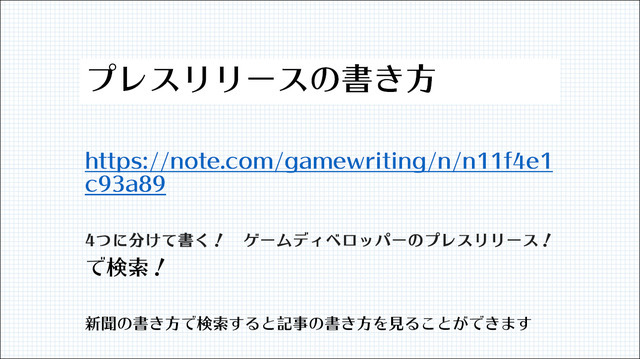

1:概要
4W(Who、When、Where、What)を入れて簡潔にまとめます。


2:ゲームの簡潔な紹介
上記4WにWhy(ゲームの目的)を加えた5Wでゲーム内容を紹介。ジャンルもここで明記します。


3:ゲーム内容の詳細
他社との同ジャンルタイトルと比べた際の独自性やセールスポイントを明記します。また、ゲーム後半になってできるようになるシステムなどに触れる際は、「■■を●個集めると、▲▲(乗り物の具体的な名称)で空を飛ぶことも」などと詳細を書いてしまうのではなく、「冒険を続ければ、空を飛ぶ乗り物も」というように詳細をあえて省く方がプレイする際の楽しみを損なわずに…というテクニックも紹介されました。


4:製品情報
ゲームの正式名称、メーカー名、価格(未定であれば価格未定と表記)、公式サイトのURLや公式SNSのアカウント名、開発者名、ステージ数、最大プレイ人数などを明記します。

5:自社情報
プレス担当者の連絡先を明記します。自社の公式サイトのURLや公式SNSのアカウント名、これまでにリリースしたタイトルを付記するのも有効です。それが新作タイトルのリリース情報でも「●●を手がけた■■社の新タイトル」というように、過去の実績が記事名に活用される場合があります。

6:プレスキット
プレスキットの内訳や用途(本リリースを掲載・紹介する目的以外での使用は禁止、など)を付記します。プレスキットをあらかじめインターネット上にアップロードしておく場合は、アクセス手段も明記します。

完成したプレスリリースの送り方についても紹介されました。各メディアのWebサイトには大抵プレスリリースの送付先が明記されているので、そこから送信します。ゲームのことを専門的に扱うメディアはもちろん、「PC(やスマートフォン)の情報がメインだが、時にはPCゲーム(やスマートフォンゲーム)の紹介も行う」ような隣接するメディアにも送信するのもひとつの手段です。
秦氏は「これからは、プレスリリースもゲーム開発の一環と捉えるのがよいと思います。PR代行サービスを利用するのもひとつの手段ですが、その場合もリリースそのものは自分たちで書く必要があります。ゲーム業界のみならず、BtoCであれば他業種のプレスリリースもとても参考になると思います」と語り、講演をまとめました。

最後に、講演後に行われた聴講者からの質疑応答を紹介します。
Q.リリースを送るメディアごとにリリースの内容を変える必要はある?
A.変える必要はありません。ただ、もらったプレスリリースを原文そのままで掲載するメディアもありますので、そういうメディアに送る際は詳細をしっかり書いておくのもいいでしょう。
Q.リリースを掲載してもらうためのコツはある?
A.極端な例ですが、リリースの発信と東京ゲームショウ、E3、gamescomなどの大型イベントの日程がかぶったら、大半のメディアはそちらを優先してしまうでしょう。そうした外部的な要因もありえますので、機会に応じてリリースを複数回発信するのが大切です。
Q.ファイル形式は何がよいか
A.これでなければだめ、というものはないと思います。ただ、製品情報(などのメディアによって差異が出ない情報)は、コピー&ペーストできるような体裁がよいでしょう。
































※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください